
小型船舶免許は国家資格です。
だから国家試験に受からないといけません。
そのために勉強をするのですが、
小型船舶免許の学校は料金も施設も内容もピンキリです。
お金を振り込んだあと後悔しないためにも、
事前に調べてから選びましょう。
だから国家試験に受からないといけません。
そのために勉強をするのですが、
小型船舶免許の学校は料金も施設も内容もピンキリです。
お金を振り込んだあと後悔しないためにも、
事前に調べてから選びましょう。
学校の種類と違い
「国家試験免除校」
と
「国家試験受験校」
東京
ハーバーは
こちら!国家試験免除校とは?
国土交通省の規定を満たして認定を受けた学校で、教員と試験官の有資格者が行う学科と実技の教習を受け、それぞれの修了審査に合格すれば、国家試験が免除されます。
教習時間も国が規定する一人当たりの最低教習時間が保障されています。
国家試験免除校の場合、修了審査結果と採点内容がその場でわかるので、東京ハーバーb.l.sの場合は、万が一、修了審査に落ちても、点数が低かった科目の補習を受けたあと、再度、修了審査を行うなど、素早く合格までサポートさせていただきます。
各校で再審査への対応が違うので、事前に問い合わせをしてみてください。
教習時間も国が規定する一人当たりの最低教習時間が保障されています。
国家試験免除校の場合、修了審査結果と採点内容がその場でわかるので、東京ハーバーb.l.sの場合は、万が一、修了審査に落ちても、点数が低かった科目の補習を受けたあと、再度、修了審査を行うなど、素早く合格までサポートさせていただきます。
各校で再審査への対応が違うので、事前に問い合わせをしてみてください。
国家試験受験校とは?
簡単にいうと、国家試験を受験しに行く手伝いをする無認可の免許教室です。
監督官庁が無いため、教える先生に教員資格は必要なく、船や設備、授業時間にも基準がないため、雑居ビルの一室や個人の自宅など環境もまちまち、学科と実技会場が遠く離れていることが多く実態はさまざまです。
また「独学コース」と称する教科書を送りつけるだけ、実技は大人数を乗せて短時間で終わる教室もあります。
いずれも、共通しているのは、授業日数が少なく価格が安いこと。
国家試験に落ちれば、再度申し込みを行いますが、再試験まで何週間も時間が開くので特に復習する事が困難な実技は更に難しくなります。
ホームページで高い合格率を宣伝していても、仲間内で作った協会で優良校認定と褒めあっても、無認可教室が国家試験の採点内容を知るべくも無く、全ては生徒の自己責任です。
監督官庁が無いため、教える先生に教員資格は必要なく、船や設備、授業時間にも基準がないため、雑居ビルの一室や個人の自宅など環境もまちまち、学科と実技会場が遠く離れていることが多く実態はさまざまです。
また「独学コース」と称する教科書を送りつけるだけ、実技は大人数を乗せて短時間で終わる教室もあります。
いずれも、共通しているのは、授業日数が少なく価格が安いこと。
国家試験に落ちれば、再度申し込みを行いますが、再試験まで何週間も時間が開くので特に復習する事が困難な実技は更に難しくなります。
ホームページで高い合格率を宣伝していても、仲間内で作った協会で優良校認定と褒めあっても、無認可教室が国家試験の採点内容を知るべくも無く、全ては生徒の自己責任です。
教習所
選びの
独学コースは安いのか?

格安の「独学コース」に6万円支払い、チョロっと操船体験するくらいなら、いっそのことネットで教科書を買って、YouTubeで実技を学んで総額2万円で国家試験を受験しても大して結果は変わらないと思います。事実そういう方が大勢いるのが現実です。
しかし、そのような勉強の結果として運よく国家試験に受かったとしても、船の操船技術が短時間で身につくことは絶対にありません。
免許取得後に、レンタルボートを借りて操船訓練をすれば、簡単に10万円単位のお金と何ヶ月もの時間がかかってしまいます。
また、船は自動車と違い、軽微な違反も全て刑事事件として書類送検されるのでリスクを理解しないといけません。
価値観の違いですが、自分が船舶免許というプラスチックのカードが欲しいのか、操船の知識と技術を身につけたいのか、はっきりと自覚した上でスクールは選ぶべきだと思います。
しかし、そのような勉強の結果として運よく国家試験に受かったとしても、船の操船技術が短時間で身につくことは絶対にありません。
免許取得後に、レンタルボートを借りて操船訓練をすれば、簡単に10万円単位のお金と何ヶ月もの時間がかかってしまいます。
また、船は自動車と違い、軽微な違反も全て刑事事件として書類送検されるのでリスクを理解しないといけません。
価値観の違いですが、自分が船舶免許というプラスチックのカードが欲しいのか、操船の知識と技術を身につけたいのか、はっきりと自覚した上でスクールは選ぶべきだと思います。
教習所
選びの
ホームページに騙されない!

ボート免許スクールのホームページに美しい南の島の写真やカッコイイ船の写真が並んでいたら要注意!
なぜなら、自分の学校の船や教室の写真を見せられないということだから。
スクールの中には、トイレも無い河原に船を係留していたり、教室が狭い雑居ビルの一室だったり、個人の自宅の居間だったりすることもあります。
教員の写真や経歴を載せていないのも要注意!単なる船舶免許を持っているだけのアルバイトが教えるスクールもたくさんあります。
挙句の果てには、自分で比較サイトを立ち上げて自画自賛するスクールなど、玉石混淆のボートスクール業界。
特に無認可スクールはGoogleのストリートビューや低評価の口コミで確認するようにしましょう。
なぜなら、自分の学校の船や教室の写真を見せられないということだから。
スクールの中には、トイレも無い河原に船を係留していたり、教室が狭い雑居ビルの一室だったり、個人の自宅の居間だったりすることもあります。
教員の写真や経歴を載せていないのも要注意!単なる船舶免許を持っているだけのアルバイトが教えるスクールもたくさんあります。
挙句の果てには、自分で比較サイトを立ち上げて自画自賛するスクールなど、玉石混淆のボートスクール業界。
特に無認可スクールはGoogleのストリートビューや低評価の口コミで確認するようにしましょう。
教習所
選びの
教習日数の違いは!?

国家試験免除の登録教習所にも違いがあります。多くの登録教習所が小型船舶免許2級の講習を2日間で行っているのに対し、東京ハーバーは3日間です。
どこが違うのでしょうか? 国が定める教習時間は、実技教習が4時間以上、学科教習が12時間以上。つまり、実技と学科の合計で最低16時間の教習が必要です(それ以下は違法です)。
これに2日間の昼食時間や試験時間(70分)を加えると、移動のない桟橋一体型の教習所でも19時間以上は必要になります。さらに、実技教習の4時間にはロープワークやエンジン点検も含まれるため、実際に操船できる時間はわずか1時間程度です。
1時間で操船できるようになると思いますか? そもそもこの日程をこなせると思いますか?——我々は、そうは思いません。
東京ハーバーでは、実技教習を朝から夕方まで8時間かけて行い、2級を3日間の日程で組んでいます。1級はさらに12時間の教習と修了審査70分が必要となるので、2日追加され合計5日の日程。Googleのレビューに夕日の写真が多いのは夕方まで操船しているから。
私たちは、知識と技術をしっかり伝えるために、本当に必要な時間を提供しています。
どこが違うのでしょうか? 国が定める教習時間は、実技教習が4時間以上、学科教習が12時間以上。つまり、実技と学科の合計で最低16時間の教習が必要です(それ以下は違法です)。
これに2日間の昼食時間や試験時間(70分)を加えると、移動のない桟橋一体型の教習所でも19時間以上は必要になります。さらに、実技教習の4時間にはロープワークやエンジン点検も含まれるため、実際に操船できる時間はわずか1時間程度です。
1時間で操船できるようになると思いますか? そもそもこの日程をこなせると思いますか?——我々は、そうは思いません。
東京ハーバーでは、実技教習を朝から夕方まで8時間かけて行い、2級を3日間の日程で組んでいます。1級はさらに12時間の教習と修了審査70分が必要となるので、2日追加され合計5日の日程。Googleのレビューに夕日の写真が多いのは夕方まで操船しているから。
私たちは、知識と技術をしっかり伝えるために、本当に必要な時間を提供しています。
教習所
選びの
教習艇も調べよう!

教習艇は教習所の「顔」。どんな教習艇が使われているのかをチェックすることも、教習所選びでは重要です。長年、国家試験で使用されてきた名艇「ヤマハLS17」は東京ハーバーにも1艇ありますが、エンジン生産の終了により、現在では90馬力の船外機を搭載した「ヤマハFR20」が主流です。
FR20は船外機のためエンジン点検が簡単で、プロペラの向きも一目でわかるなど多くの利点があります。ただし、後進時の舵効きが悪いという欠点も。教習艇としては80点ほどでしょうか。東京ハーバーではこのFR20を2艇保有しています。
さらに、アルミ製船体を持つトヨタの「ポーナム26L」も2艇あります。ディーゼルエンジンの船内外機でエアコン付き。少し大柄ですが走波性が高く、荒天時や寒い時期には主力として使用されます。どんな教習艇を用意しているかを見れば、教習所の姿勢が見えてきます。
FR20は船外機のためエンジン点検が簡単で、プロペラの向きも一目でわかるなど多くの利点があります。ただし、後進時の舵効きが悪いという欠点も。教習艇としては80点ほどでしょうか。東京ハーバーではこのFR20を2艇保有しています。
さらに、アルミ製船体を持つトヨタの「ポーナム26L」も2艇あります。ディーゼルエンジンの船内外機でエアコン付き。少し大柄ですが走波性が高く、荒天時や寒い時期には主力として使用されます。どんな教習艇を用意しているかを見れば、教習所の姿勢が見えてきます。
教習所
選びの
教習水域と教習桟橋も
チェック!

教習艇だけでなく、教習を行う「桟橋」や「教習水域」も重要なチェックポイントです。教習水域が河川の場合は流れがあり、雨天後には流れが速くなったり、ゴミが流れてきたりすることもあります。一方で港内は管理されていて流れがなく波も穏やかですが、規制が厳しく、東京港では「教習目的の桟橋」は許可されていません。
そのため、多くの教習所では、コンクリートの護岸などを桟橋に見立てて教習を行っています。コンクリート壁近くは引き波の影響があり危険です。河川には流れがあり、港湾は規制が厳しい――それぞれに一長一短があります。
日本は世界で最も水辺の規制が厳しい国です。海洋国家とは言われていても、誰もが水辺を使用できる「親水国家」とは言えません。水辺は国民のものではなく、漁協などの特定の既得権益者のものとなっているのが現実です。
東京ハーバーは、「芝浦アイランド」という官民共同の街づくりの中で、東京港内で唯一「教習専用の自社桟橋」が許可された教習所です。これは、都の規制緩和政策の一環として、公共性の高い活動を行うことを条件に特別に許可されたもので、教習事業に加え、小学校向けの環境学習や海洋少年団の運営支援、自治体の防災支援、海上保安庁との連携によるパトロールなど、幅広い社会貢献も行なっています。
そのため、多くの教習所では、コンクリートの護岸などを桟橋に見立てて教習を行っています。コンクリート壁近くは引き波の影響があり危険です。河川には流れがあり、港湾は規制が厳しい――それぞれに一長一短があります。
日本は世界で最も水辺の規制が厳しい国です。海洋国家とは言われていても、誰もが水辺を使用できる「親水国家」とは言えません。水辺は国民のものではなく、漁協などの特定の既得権益者のものとなっているのが現実です。
東京ハーバーは、「芝浦アイランド」という官民共同の街づくりの中で、東京港内で唯一「教習専用の自社桟橋」が許可された教習所です。これは、都の規制緩和政策の一環として、公共性の高い活動を行うことを条件に特別に許可されたもので、教習事業に加え、小学校向けの環境学習や海洋少年団の運営支援、自治体の防災支援、海上保安庁との連携によるパトロールなど、幅広い社会貢献も行なっています。
社長メッセージ
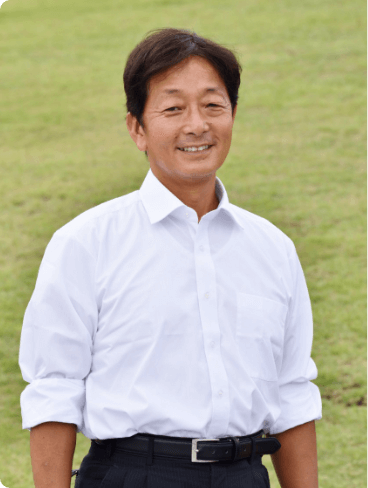
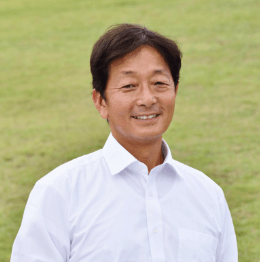
榎本 茂
東京ハーバー・
ボートライセンス・スクール
株式会社ミナモ
代表取締役社長
大学を卒業して英国の国営企業オースチンローバーに入社後、ジャガーの日本法人の立ち上げに参加。英米以外の国におけるNo1セールスとして表彰される。
40歳でサラリーマンを辞め、釣りを仕事に転向。世界最大のルアーメーカーであるフィンランドのラパラ社と専属契約を結び、プロアングラーとして主演するテレビ番組を持ち、自身の名を冠した釣具をプロデュユースし、連載コラムや本の執筆など幅広く活動する。
45歳で東京・港区に船舶免許の学校を設立し、自身も教官・国家試験官として教壇に立つ。さらに50歳からは政治家として議員活動を開始。東京都水上安全条例の70年ぶりの制定を主導し、その内容は新しい船舶免許の教科書や試験問題にも反映されている。
「日本は親水国家を目指すべき」という信念のもと、船舶免許事業にとどまらず、自社開発の電気推進船を活用した地域の小学校での運河学習、カヌーを用いた海洋少年団の活動支援、自治体との防災協定、海上保安部と連携したパトロールなど、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。
40歳でサラリーマンを辞め、釣りを仕事に転向。世界最大のルアーメーカーであるフィンランドのラパラ社と専属契約を結び、プロアングラーとして主演するテレビ番組を持ち、自身の名を冠した釣具をプロデュユースし、連載コラムや本の執筆など幅広く活動する。
45歳で東京・港区に船舶免許の学校を設立し、自身も教官・国家試験官として教壇に立つ。さらに50歳からは政治家として議員活動を開始。東京都水上安全条例の70年ぶりの制定を主導し、その内容は新しい船舶免許の教科書や試験問題にも反映されている。
「日本は親水国家を目指すべき」という信念のもと、船舶免許事業にとどまらず、自社開発の電気推進船を活用した地域の小学校での運河学習、カヌーを用いた海洋少年団の活動支援、自治体との防災協定、海上保安部と連携したパトロールなど、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。
